|
「もうこんな時間か…」
いつもそうだ。気がつくと終わりにしなければならない時間がやってくる。
走り去る車の陰が長い菱形を描きながら短い秋の昼下がりを夕暮れに染めていく。
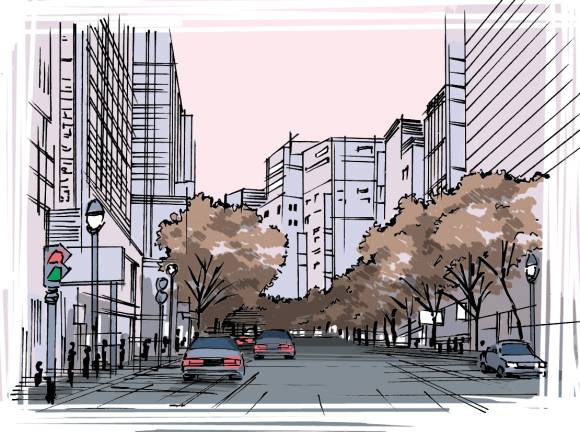
「さぁ、行こうか」
飴色に染まる街り中へ踏み出せば、もう半袖で歩く人などいない事に嫌でも気付かされる。
脳裏をよぎるのは懐かしいメロディ…。そんな自分が馬鹿馬鹿しく思えて苦笑いをする。
沸きあがろうとする記憶をふり払い、少し足早に歩いてみる。
こんな時、映画の主人公なら洒落たバーで酒でも呑むのだろうが
あいにく僕は酒が呑めない。
つい5分前までは愛しい人と一緒だった。
彼女にとって楽しいデートではなく、つらい時間になってしまった。
最後に見た彼女が泣き顔ではなかった事は僕にとって多少の救いにはなっていた。
悪いのは彼女ではない。
ただ、ラヴアフェアーではなく純粋に愛し合えたという事実が
僕の罪悪感を数倍にしている事も事実だった。
お互いの環境や感情はじゅうぶんに二人を許していたはずだったが
それ故に二人の関係は少しずつ噛み合わなくなっていった。
「またこんな季節がやってきた」
そう思わざるを得ないほど、あのメロディは頭から離れない。
美しいメロディが…腹立たしいほどに美しく…鮮明に流れていく。
キーを捻る。乾いたエンジンの音が無機質なコンクリートの駐車場に反響する。
「いつか…優しくなれたら…あの曲を聴きながら走れるかな…」
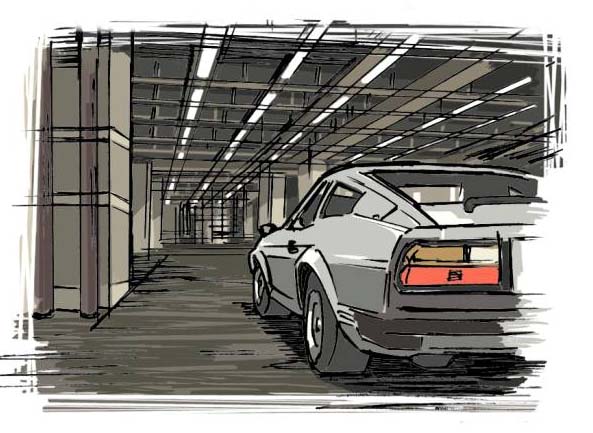
− 終 −
|